
こんにちは、存在しないモノを描いている妖怪、洋伯(よはく)です。
私は普段、存在しないモノをキャラクター化したり見たことのない世界を創ったりしています。
今回は怪談の妖怪青行灯について調べてみました。
百物語をすると怪異が起こる
百物語という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
この妖怪青行灯は百個の怪談を話しおわったあとに現れると言われています。
百物語とは現代広まっている噂によると、まず百本の蝋燭ろうそくに火をともします。
そして人が集まって一人ずつ交互に怪談を語って、話し終わるごとに蝋燭の火を一本ずつ消していくというものです。
どうやら怪談や怖い話というのは怪異を集めるようで、百個の怪談を話し終わって百個の蝋燭を消すと何やらよくない怪奇な現象が起きるだとか、妖怪や幽霊が出るとされています。


百物語について調べてみると、どうやら当初は現在広まっているようなやり方ではないことが分かりました。
青行灯を使って百物語をした話
”怪談老の杖”という本に厩橋(今の群馬県前橋市)で百物語を行った話があります。
原文が国立国会図書館のデジタルコレクションで読めるので是非読んでみてください。
→原文はこちら(リンク先の”怪談老の杖”の章の“厩橋の百物語”という話のところに書いてあります。)

以下読みやすく現代語や解説を入れた厩橋の百物語の内容になります。
百物語の話 (怪談老の杖より)
延享のはじめ(1740頃)、厩橋の城内にて雨のものすごく降るある晩の話。
中原忠太夫という勇敢な男が”妖怪はいるのかどうか”と城内の若い者たちに質問したところ、みなそれぞれに意見します。
それをみた忠太夫は、”こんなに雨も降っていて何となく凄まじい雰囲気なので、噂の百物語というものをやってみて妖怪が出るかどうかためしてみよう”と提案しました。
みな若いということもあってか早速やってみることとなりました。

ひえ~! 何が起きるのでしょうか。
百物語の正式な方法は、皆がいる部屋で一人ずつ一話怪談を話していき、話し終えた者は別室に行き行灯に青い紙を貼ったものの中の、百個いれてある灯心の一つを消し、その部屋に置いてある鏡に自分を映してから皆の部屋に帰ってくるという一種の肝試しのようなものです。
行灯とは昔の照明で、和紙を貼ってある木枠に中に油の入った皿が置いてあり、そこに灯心といわれる紐ひもが浸かっていてその紐ひもに火がついています。

忠太夫たちは、正式な方法通りに5つの真っ暗な部屋を通り抜けて、奥の大書院(客間用の広い部屋)に青い紙を貼った行灯に灯心百本をともし、その横に鏡を立て、今いる部屋で怪談を話し始めました。

忠太夫から怪談がはじまり、一人ずつ話しては次々に灯心を消しに5部屋先の大書院へ行き、鏡に自分の姿を映してから帰ってくる。
灯心は一本一本消されていき、徐々に部屋は暗くなってきました。
夜八ツ刻(丑ノ刻)(深夜の二時くらい)になった時に八十二話の怪談を話し終えていましたが、まだ特に異変は起きていません。
いよいよ真っ暗になってきた八十三話目であることが起きます。
八十三番目の話を終えた忠太夫は、真っ暗な部屋を一つ一つ通り過ぎ、行灯のある大書院へ入る襖を開けた時に何気なく振り返ると、右の方の壁に白いものが見えました。
近寄って触ってみると絹の裾と手にあたります。
怪しいと思って見上げると女の首つり死体が天井に下がっていました。

”これが妖怪というものであろうか。”
忠太夫は勇気のある男だったので、引き続き大書院へ向かい灯心を消して皆の部屋に戻ろうとしましたが、戻りがけに見るとまだ白いものが見えていました。
その後も百物語は続けられましたが、大書院へ行った誰一人として忠太夫が見た妖怪について言う者はいません。
忠太夫は”自分以外にこの妖怪は見えないのだろうか。それとも自分のように妖怪を見たが黙っているのだろうか”と考えていました。
そんな折、すべての怪談を話し終えると筧甚五右衛門という男が口を開きました。
彼の顔色は悪く、何だか気分も悪そうです。
”誰か怪しいものを見た者はいないか。私は見たんだが黙っていた。皆はどうだ?”
”私は八十三話目のときに見た”と忠太夫が言う。
”それは女の首吊り死体ではないか”と皆が口をそろえて言う。
どうやら皆が同じ妖怪が見えていることが分かったので、皆で見に行ってみるとそこには
18,9歳くらいの女が白無垢(結婚式に女性が着る、もしくは死体に着せる白い着物)を着て、白縮緬(帯の名前)を締め、ぼさぼさの乱れ髪で首をつっていました。
誰かが”死体を下ろそう”と言いましたが、襖を閉めてこの妖怪がどうなるか見てみようということになって皆で妖怪と思われる首吊り死体のそばに座って様子をうかがっていました。
しかし朝になり空が明るくなってきてもその妖怪は消えません。
やはりただの死体ではないかと役人をつれてくると、この女の首吊り死体は島川という中老の女であることが分かったのですが、この場所は女中のくる場所ではなかったのでやはり妖怪の類だろうと判断しました。
しかし万が一間違いがあった場合にただでは済まされないということで念のためにその島川という女中に会いにいくことにしました。
結局島川は体調不良で休んでいたけれども、首は吊っておらず生きていました。
そして首つり死体の妖怪がいた部屋へ戻るとその妖怪は跡形もなく消えていて、皆に聞くと気づくと妖怪は消えていたといいます。
ただ妖怪が出た、というだけでこの話は終わりそうですが実は続きがあります。
その島川という女中はそれからしばらくして、人を恨んで首を吊って亡くなってしまったというのです。
百物語で現れた首吊り死体の妖怪はその女中が死ぬ前兆だったのか、はたまたその妖怪に呪いころされたのかは誰もわからない。
この話はのちに藩を出て剣術の先生をしていた忠太夫に聞いた話です。
妖怪”青行灯”とは
忠太夫が行ったように百物語をすると不思議な現象がおきるのですが、その時に起きる怪異の総称を青行灯と呼ぶようです。
見たままの通り、青い紙を貼った行灯が語源のようです。

なので特定の妖怪を指す名前ではなく、百物語を行ったときに現れる怪異の名前ということになります。
ちなみに忠太夫たちが噂に聞いていた百物語の内容というのは、寛文6年(1666年)に編まれた仮名草子”伽婢子”終章に書かれているものです。
以下内容です。
京都のとある場所で、5,6人で百物語をしていると70話目くらいになったとき、窓の外の雪が降る中を数千ともわからない蛍火が飛び交って家の中に入ってきました。
その蛍火は家に入ってくるとなんと直径150センチくらいある火の玉であることがわかり、それが天井にあたって落ちる音が雷が落ちたような音で皆気を失ってしまいました。

両方の話は聞いているだけだとあまり怖くはありませんが、昔は電気がなく本当に真っ暗だったので、想像以上に滅茶苦茶怖かったんだろうなと思います。
現代はどこへ行っても明るいのであまり夜中の怖さは感じないですが、当時夜中に百物語をするというのは非常に怖い肝試しだったのでしょう。
まとめ
妖怪青行灯とは、特定の妖怪を指すものではなく百物語をするなかで起こる怪異の総称です。
また青行灯という名前の語源は、肝試しとして百物語をする際に行灯の紙を青くしてその光で照らされた自分鏡に映すということをしていたことから青行灯と言われています。
昔は電気もなく本当に真っ暗だったと思うので、その中で青い紙の行灯だけの照明はとても暗くて怪しかったはずです。
さらに一本ずつ灯芯を消していくので段々と真っ暗になっていきます。

僕は怖くて絶対にやりたくないですね。
妖怪青行灯の話から分かることは、怖い話をすると妖怪が寄ってくるということです。
こういうブログを読んでいても妖怪は寄ってくるのでしょうか。
記事/イラスト: 洋伯(よはく)
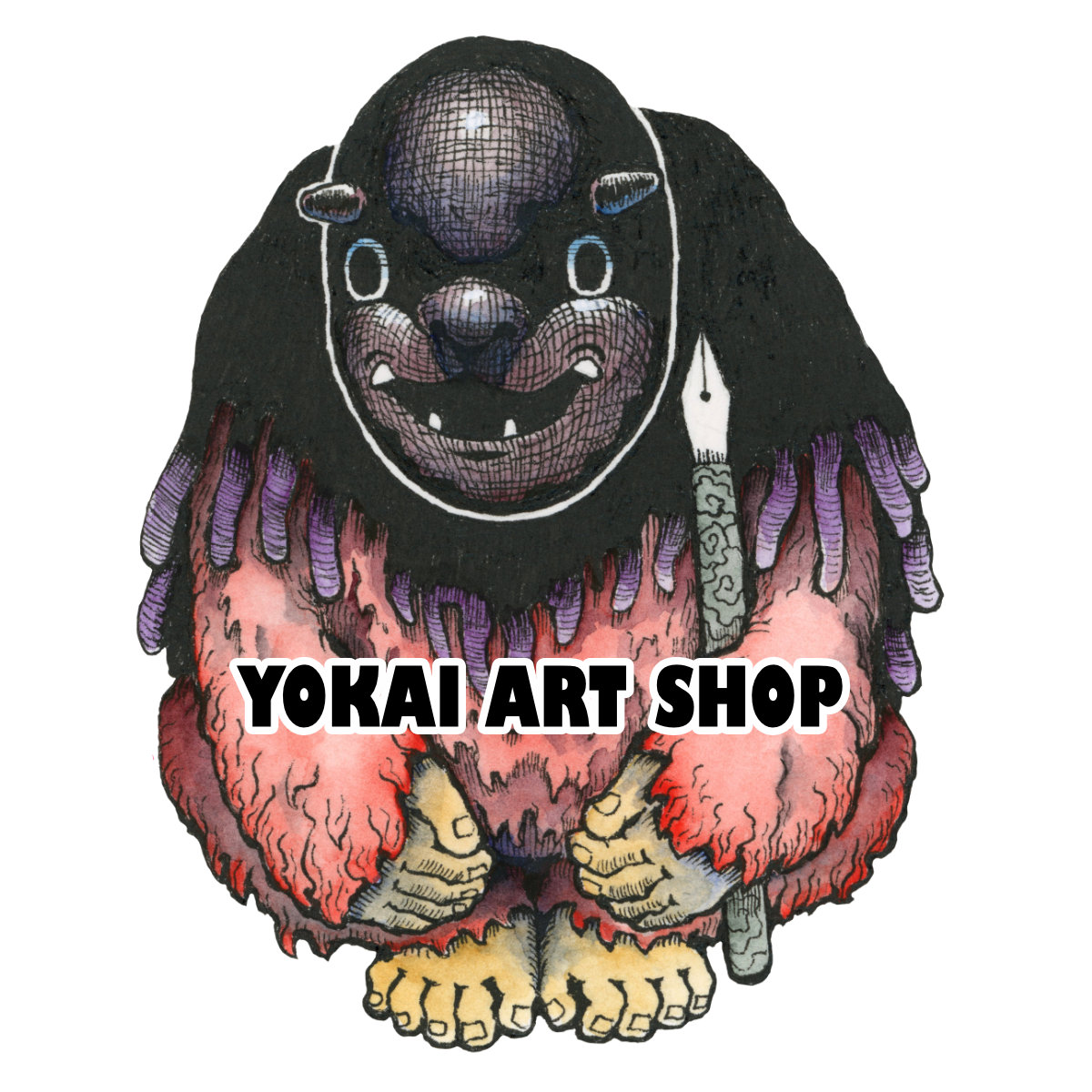


コメント